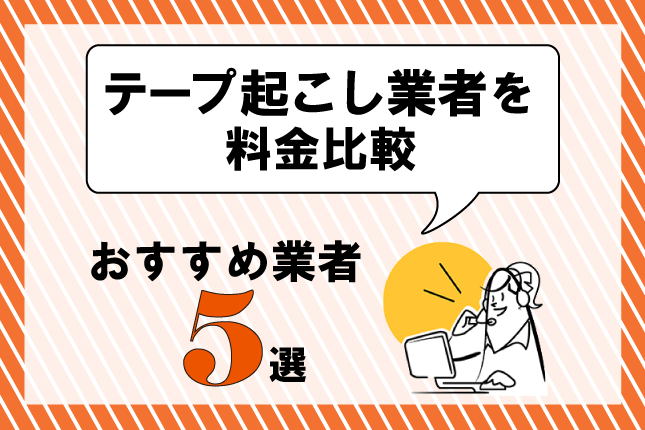テープ起こしに使われる校正記号
テープ起こしで文字に直した原稿は、場合によっては聞き漏れや聞き間違いなどで、文章が間違っているケースがあります。特に日本語の場合、同じ音で違う漢字などもたくさんあるため、漢字の変換ミスで全く違う文章になってしまう、ということも起こり得るのです。そのために必要なのが校正作業、そして校正を行う上では「校正記号」と呼ばれる特殊な記号を用いていくのが一般的です。ここでは、校正記号について紹介していきます。
基本的な校正記号
逆斜線
左上から右下に向かう斜線を用います。これは、文章中の文言を修正したい場合に、修正する文字に逆斜線を入れ、横線でつないだ後に空白部分に修正すべき文言を入れる、というものです。また、文言そのものを外してしまいたいときには「トル」と入れ、スペースを詰めるときには「ツメ」と書き入れます。いずれもカタカナでの修正となります。
Y記号
「Y」の文字を使い、文字と文字の間に新しく文字を挿入する場合に使用するものです。「Y」の頭の部分の上に差し込みたい文言を書き記します。
「記号
文章を指定の場所で改行したいときに入れる記号です。文章の途中に入れることで、そこから行を変えるように指示を出すことになります。ちなみに段落改行であれば、「の左下線から横線を追加するような形になります。
改行をした際に、字下げをしたくない場合は「下ゲズ」または「天ツキ」と指示を入れる必要があります。
S記号
文字を入れ替えるときに使う記号です。隣接している文字を入れ替える場合、「S」の字の囲われている部分にそれぞれの文字を入れることで、その二つの前後を入れ換える、という指示になります。
振り仮名の追加
振り仮名を追加したい際は、振り仮名をつけたい文字の上に線を引きます。その線を余白まで伸ばして、振り仮名を記入します。振り仮名の上には「⌒」の記号をつけましょう。まとめ
ここでは、校正作業の中で特によく使われる指示記号について、いくつか紹介しました。ただし、校正記号には他にもいろいろなものがあるので、校正担当者であればできる限りそれぞれの記号の意味を知っておく必要があるでしょう。
校正はテープ起こしをするにあたって、切っても切れない作業の一つとなります。一つでもミスを見落としてしまうと、文章の意味が正しく伝わらなかったり、全く違う意味の文章になってしまう可能性もある重要な作業。校正作業にあたる人は、そうした責任感をしっかりと認識した上で、校正作業にあたることが大切です。またミスに関しては、校正記号を使いこなし、きちんと担当者が分かる形で修正指示を出せるように心掛けましょう。
(60分を3営業日納品の場合)
- テープ起こし会社カタログ
- テープ起こし依頼プラス
- コエラボの口コミ評判
- アトリエ・ソレイユの評判
- 東京反訳の口コミ評判
- シーズンソリューションの評判
- ACNの口コミ評判
- 京都データサービスの口コミ評判
- クロスインデックスの口コミ評判
- テープリライトの口コミ評判
- アーク写本の評判
- ボイテックスの評判
- ジムプランの評判
- 大和速記情報センターの評判
- モジフルの口コミ評判
- テープライターサービスの評判
- 東洋速記の口コミ評判
- メディアJの口コミ評判
- mojicaの口コミ評判
- クリプトンの口コミ評判
- JOINTEX(ジョインテックスカンパニー)の口コミ評判
- ブレインウッズの口コミ評判
- 佐藤編集事務所の評判
- VoXTの口コミ評判
- 株式会社ドルフィンの口コミ評判
- オフィスクレストの評判
- 文書システムサービスの口コミ評判
- ユウエスプラニングの評判
- オフィスモリの評判を調査
- メディアオーパスの口コミ評判
- イデアプラスの評判
- アミットの評判
- 名北ワードの口コミ評判
- ボックスタブの評判
- 音声工房 フィールド55の評判
- テープ起こし新潟の評判
- エルセクレタリーの評判
- 株式会社アドレス
- オフィスなかやま
- さくらい屋
- 東海文書処理
- デック
- ワードワープ
- ビーコスの評判
- エムストーン
- 会議録研究所
- サウンドクロップ
- ピーシーウエーブ
- 扶桑速記印刷株式会社
- KATO Office
- マキ朝日データサービス
- エサップ
- コーディ
- アート録音
- 日本コンベンションサービス(JCS)
- エディテージ
- 津軽速記
- オフィスコキリコ
- 早稲田速記株式会社
- タイピングベース
- ミュープロダクション
- クリムゾン インタラクティブ・ジャパン
- おふぃす・てのん
- NPO法人ぺりの邑 ひびき工房
- アルファテキスト
- ハルクアップ
- アミー
- office+Kai
- aiwords(アイワーズ)
- トライアングル西千葉
- LanguageFOREST
- 速記センターつくば
- 業者に依頼する前に…知っておきたいテープ起こしのサービス内容
- テープ起こしのリライト・記事作成のポイントは?
- 文字起こしの代行について
- テープ起こしに使われる校正記号
- テープ起こしと速記の違いとは?
- テープ起こしの仕事を受ける際に必要なスキル・道具
- テープ起こし業者にできること
- テープ起こしの種類
- 料金相場
- 発注時のポイントと注意点
- 依頼から納品までの流れ
- 格安におさえるコツ
- 録音のコツとは?
- 初心者にありがちなテープ起こしの失敗例
- 会議やセミナーなどを音声データでまとめておくことのメリット
- テープ起こしに便利なツールやアプリと問題点
- 多言語のテープ起こしについて
- テープ起こしにかかる手間と原因