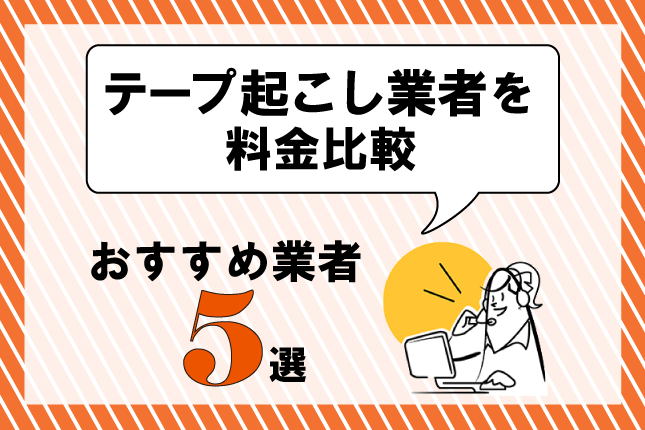初心者にありがちなテープ起こしの失敗例
テープ起こしは、特別なスキルがなくても誰でも簡単にできると思われているかもしれません。
しかし、人間が話している言葉を文字に起こすということは案外難しく、初心者の方が対応すると、専門用語が多く意味が分からなかった、録音状態が良くなかった、などという理由で本来の会話とはずれた内容になってしまうことが多々あります。
テープ起こしは実は技巧が必要な職人の仕事なのです。では初心者にありがちなテープ起こしの失敗例とはどういうものなのでしょうか?
納期に間に合わない!

仕事を受ける側としてそもそもの話になりますが、初心者にありがちなテープ起こしのミスで最も多いのが、この納期を守れない!というものです。
これは様々な理由がありますが、代表的なものは以下のものです。
想像よりも時間がかかった
初心者の人は、自分がテープ起こしをする時にどのくらい時間が必要なのかをまだ分かっていないことが多いです。
「文字を起こすだけだし、タイピングも自信があるし・・・」と見積もった予定時間より大幅に時間がかかるのがテープ起こしなのです。
経験を積んでプロと言えるほどになると、ざっと最初の音声を聞いてどんな内容かを聞くことで、自分がどのくらいの時間で仕上げられるのかが正確にわかるようになります。
聞き取れない言葉で止まってしまった
初心者が納期に間に合わない理由として、聞き取れない言葉や音声を聞こうとしてその場で何度も何度も繰り返し聞いて作業がストップし、納期に間に合わない、ということがあります。もちろんプロでも聞き取れない言葉はありますが、その場合初心者のようにずっとしつこく聞き返さずに、印をつけて先に進みます。
先に進むことで同じ言葉をもっと明瞭に発言している場面に出会うかもしれませんし、会話の流れでその言葉がふと浮かんで来ることもあるからです。
聞き取れない言葉で止まるというのもテープ起こしの初心者にありがちな失敗です。
適切な「ケバ取り」ができていない
対談やインタビュー、講義や講演会などの文字起こしを発注する際、「ケバ取り」を希望される依頼者は非常に多いでしょう。
一般的に会議の内容を把握したり、会話の内容の理解を重視する際のテープ起こしではケバ取りを行うケースが多いのですが、これが初心者には最初の難関になります。
ケバ取りとは、不必要な相槌や、不要な語句、言い澱みや言い間違いなどを取り除き読みやすくする作業ですが、この判断は場数を踏んだプロでないと非常に難しいと言われています。
相槌や言いよどみ、「あー」や「えーっと」、言い間違いなどを全て書き起こす「素起こし」であればまだ初心者が膨大な時間をかければ可能ですが、ケバ取りとなると、どこまで取り除いていいのか、また取り除いた後の繋がらない文面をどうすればいいのかの迷いが生まれ、結局中途半端で見づらいものが納品されてきてしまう可能性があるのです。
整文が未完成
議事録や会社の会議録などの文字起こしを発注する場合、「整文」という作業を行うことになりますが、初心者にありがちな失敗として整文の加減が分からないということが挙げられます。
整文とは、ケバ取りをしたテキストを読みやすく意味の通った文体に整えていく作業です。つまり口語体から文語体に整えていくのですが、これも初心者にはほぼ不可能な作業です。
語体を変えるだけなのに、読みづらくなってしまったり、最悪の場合は意味がどんどんずれてしまい本来の意図とは違う意味で勝手に解釈して内容が若干書き換わってしまうという大きな失敗も起こるので、こと整文に関しても信頼できるプロに依頼することをお勧めします。
表現のゆらぎのチェックができていない
小説など、読み物として仕上げる文章には、表現のゆらぎのチェックが綿密に行われています。これは文字起こしでも同じことで、プロが仕上げた文字起こしでは、ここまできちんと作成するのが基本です。これができていないのが、初心者にありがちな失敗の一つ。
表現のゆらぎとは、一連の文の中で、漢字とひらがなの表記が統一されていないことを指します。例えば、「かわいい猫」と「可愛い猫」、はたまた「かわいいネコ」などが混在している状態です。
文章の完成度が低く、発注者の方が何度も修正する必要があり非常に手間がかかります。
組織としてテープ起こしをやっているプロの業者や、この道を専門として仕事をしているプロはこういった間違いが起こりません。
専門のソフトを使用して間違いをチェックしたり、人の目でダブルチェックすることで納品される原稿の精度を高く保つことができるからです。
レイアウトが雑然としている
初心者の内は聞き取って文字に起こすのに必死になってしまい、レイアウトまで気が回らないことがあります。しかしただ文字を並べただけではとても読みにくい記事になってしまします。
そのため内容によってレイアウトを変えて読みやすいようにしましょう。
また「!」「…」などの記号の表記の指定があるのか確認もしておくのがおすすめです。
【対談の場合】
対談の場合は話し手が最低2人はいるため、「誰の発言であるか」ということを明確にしなければいけません。
そして基本的には「話し手」の話題に重点をおきます。そして両者の話のバランスが取れるような記事を書きましょう。
【インタビュー記事の場合】
インタビュー記事の場合は聞き手はうなずいていることも多いので、話し手の話を重点的に記すようにします。
また一旦全部通して聞いてから、記事の構成やレイアウトを考えて文字を書き起こすのもおすすめです。
そして話し手の口調をどこまで再現するのか、聞き手の相槌も起こすのかどうか、笑い声なども再現するのかという点も確認しておきましょう。
【段落や改行はどうするの?】
初めのうちはどこで改行してよいのか、段落はどう分けたら良いのかわからない場合も多いと思います。テープ起こしの場合は基本的に改行は「話題が変わる」時に行います。
しかし改行が多すぎる文章は逆に読みにくくなってしまいますので、気をつけましょう。
段落は複数の文章で構成されています。基本的に「新しい話題」になった時に段落を分けます。1つの話題で1つの段落にすれば読み手にもわかりやすくなります。
【記事ができた後に読み直す】
記事ができたら一度読み直しましょう。誤字脱字のチェックや、文章は読みやすくなっているか、レイアウトは分かりやすいかなどを確認します。
また声に出して読むと気づきやすくなります。
聞き取れなかった際の対処法が統一されていない

テープ起こしを行う際には、どうしても聞き取れなかった部分が出てくると思います。
その聞き取れなかった部分の対処法(記述)が統一されていないと、あとから混乱を招くもととなります。聞き取れなかった際の対処法はクライアントにまず確認しておきましょう。
もし指定されている場合はそれに従います。それでは例えばどんな失敗例が考えられるのでしょうか。
【自己判断で記述してしまっている】
依頼される音声の中には、聞きなれない用語や専門用語が出てくるものも多くあります。その際には決して自己判断でわからないのに当てはめたり、記録を消したりしないようにしましょう。
特に記録性の高い議事録などは要注意です。まず一旦全部を聞いて会話の全体像を把握してからテープ起こしを行いましょう。
また専門用語が多用される場合は事前にクライアントに用語集がないか尋ねたり、インターネットで情報収集を行ったりするおすすめです。
【聞き取れかった場所の秒数が書かれていない】
聞き取れなかった部分の記し方は、クライアントにまず確認しましょう。特に指定がない場合は、タイムコード(00:00:00)を示しておくと分かりやすくなります。
聞き取れなかった場所の時間が書かれていない場合は、後から探すのが大変になってしまいます。
タイムコードが記入されていればどの辺りを聞けば良いのかすぐに分かるので、できるだけこのタイムコードを記入するのは必須にした方がよいでしょう。
特に初心者の時は1時間を超えるデータなのにこのタイムコードが記入されていない場合が多いので注意しましょう。
性能の低い機材を使ってしまう
現在では音声ファイルなどで依頼されることが多いと思います。しかし性能の低い機材や、快適に巻き戻しなどが行えない専用のソフトを使っていない場合は、テープ起こしに余計な時間がかかってしまいます。
特にテープ起こしの音源には、音声だけでなく様々な雑音も録音されています。そのため安価な機材ではうまく聞き取れない場合もあります。
特に始めたばかりのころは安価なイヤホンやヘッドホンを使っている場合もあるので、うまく聞き取れない場合は買い換えるのがおすすめです。
【どんなイヤホンが良いの?】
基本的には好みで、長く着けていても違和感の無いものが良いでしょう。イヤホンなら「カナル型」がおすすめです。耳に差し込む形なので、周囲の音が遮断され聞き取りやすくなっています。
またヘッドホンの場合は、より遮音性の高い「密閉式」がおすすめです。耳全体を包み込むので、より音に集中することができます。デメリットとしては持ち歩くのに不便だという点です。
いずれも装着感によって好みが分かれますので、事前に試着をして選びましょう。
録音時間と対象時間は異なることもある
音声ファイルの録音時間とテープ起こしの対象時間は異なることがあるので、確認することが大切です。
例えば60分録音されたものでも、実際に文字に起こす時間は3分~56分15秒までと指定されていることがあります。
特にインタビュー記事の場合などは、冒頭に挨拶部分や本題への導入部分がある場合も多くなっています。余分な部分も入れてしまわないように、必ず対象時間は明確にしておきましょう。
またクライアントによってインタビュアーと話し手の表記も指定されている場合があります。事前に細かいルールなども確認しておきましょう。
まとめ
テープ起こしはアルバイト感覚で誰にもでもできるイメージを持っていらっしゃる方も多いかもしれません。
しかし、このテープ起こしという作業にはタイピング能力や国語能力はもちろんのこと、語彙力の高さや、会話の流れを掴む勘の良さ、仕事の丁寧さなど多くの要素が必要です。
初心者にありがちな間違いをあげましたが、実際もっとたくさんの間違いが起こりえます。テープ起こしとは、インタビューの記録、会議の証拠、講義の内容の記録と、大切な一次資料となるものです。
テープ起こしを元に社報を編集したり、論文を執筆したり、記事を書いたり活用されるのではないでしょうか?
その際、初心者や素人が作成したテープ起こしを完全に信頼することができるでしょうか?
初心者に発注する際は、そういったリスクをしっかり考えた上で発注する必要があるのです。
(60分を3営業日納品の場合)
- テープ起こし会社カタログ
- テープ起こし依頼プラス
- コエラボの口コミ評判
- アトリエ・ソレイユの評判
- 東京反訳の口コミ評判
- シーズンソリューションの評判
- ACNの口コミ評判
- 京都データサービスの口コミ評判
- クロスインデックスの口コミ評判
- テープリライトの口コミ評判
- アーク写本の評判
- ボイテックスの評判
- ジムプランの評判
- 大和速記情報センターの評判
- モジフルの口コミ評判
- テープライターサービスの評判
- 東洋速記の口コミ評判
- メディアJの口コミ評判
- mojicaの口コミ評判
- クリプトンの口コミ評判
- JOINTEX(ジョインテックスカンパニー)の口コミ評判
- ブレインウッズの口コミ評判
- 佐藤編集事務所の評判
- VoXTの口コミ評判
- 株式会社ドルフィンの口コミ評判
- オフィスクレストの評判
- 文書システムサービスの口コミ評判
- ユウエスプラニングの評判
- オフィスモリの評判を調査
- メディアオーパスの口コミ評判
- イデアプラスの評判
- アミットの評判
- 名北ワードの口コミ評判
- ボックスタブの評判
- 音声工房 フィールド55の評判
- テープ起こし新潟の評判
- エルセクレタリーの評判
- 株式会社アドレス
- オフィスなかやま
- さくらい屋
- 東海文書処理
- デック
- ワードワープ
- ビーコスの評判
- エムストーン
- 会議録研究所
- サウンドクロップ
- ピーシーウエーブ
- 扶桑速記印刷株式会社
- KATO Office
- マキ朝日データサービス
- エサップ
- コーディ
- アート録音
- 日本コンベンションサービス(JCS)
- エディテージ
- 津軽速記
- オフィスコキリコ
- 早稲田速記株式会社
- タイピングベース
- ミュープロダクション
- クリムゾン インタラクティブ・ジャパン
- おふぃす・てのん
- NPO法人ぺりの邑 ひびき工房
- アルファテキスト
- ハルクアップ
- アミー
- office+Kai
- aiwords(アイワーズ)
- トライアングル西千葉
- LanguageFOREST
- 速記センターつくば
- 業者に依頼する前に…知っておきたいテープ起こしのサービス内容
- テープ起こしのリライト・記事作成のポイントは?
- 文字起こしの代行について
- テープ起こしに使われる校正記号
- テープ起こしと速記の違いとは?
- テープ起こしの仕事を受ける際に必要なスキル・道具
- テープ起こし業者にできること
- テープ起こしの種類
- 料金相場
- 発注時のポイントと注意点
- 依頼から納品までの流れ
- 格安におさえるコツ
- 録音のコツとは?
- 初心者にありがちなテープ起こしの失敗例
- 会議やセミナーなどを音声データでまとめておくことのメリット
- テープ起こしに便利なツールやアプリと問題点
- 多言語のテープ起こしについて
- テープ起こしにかかる手間と原因